- ウィズコロナのライフプランニング①
- ウィズコロナのライフプランニング②
- ウィズコロナのライフプランニング③
- ウィズコロナのライフプランニング④
- ウィズコロナのライフプランニング⑤
- コロナ禍のライフプランニング①
- コロナ禍のライフプランニング②
- コロナ禍のライフプランニング③
- コロナ禍のライフプランニング④
- コロナ禍のライフプランニング⑤
- コロナ禍のライフプランニング⑥
- コロナ禍のライフプランニング⑦
ウィズコロナのライフプランニング④
暮らしとお金 ケース4
高井さんは、56歳の主婦で、パート勤務をしていて自身の年収は100万円です。
コロナ自粛で夫が家にいるようになったのをきっかけに'コロナ離婚'を真剣に考えていて、これを機に地方の実家にUターンして、母親と同居しようかとおもっています。自身は、5年間会社員として勤務し、その期間の平均年収は360万円で、30歳のときに2歳上の会社員であった夫と結婚し、子どもはすでに独立しています。
状況把握のためのチェックポイント
- ・収入の見通し
- ・財産分与を含め、金融資産はいくらあるか
- ・実家に戻った場合、仕事は見つかるか
- ・年金の合意分割は可能か
- ・実家の相続で問題が起きないか
離婚後の生活費と老後資金について考える必要があります。生活費は、離婚の際の財産分与、高井さん自身の資産、そして働いて得る収入で賄うことになります。
地方の実家にUターンした場合、新たに仕事を見つけて収入を得ることができるかを慎重に確認したいです。
年金については、婚姻期間中の夫の報酬比例部分を分割してもらうことができます。2008年4月1日以降は3号分割として報酬比例部分の2分の1、それ以前の分については夫の合意を得たうえでの分割となります。
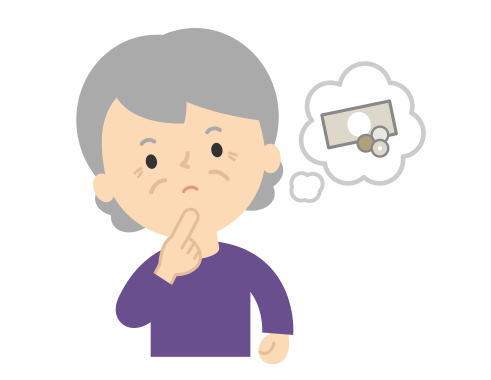
離婚した場合の年金額
夫58歳、妻56歳、婚姻期間26年で離婚。夫は退職まで平均年収500万円で40年間勤務の見込み、妻は平均年収360万円で5年間勤務(結婚後、第3号)
基本の年金額(万円)
| 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 合計 | |
| 夫 | 78 | 110 | 188 |
| 妻 | 78 | 10 | 88 |
| 2人の合計 | 276 | ||
離婚しない
| 世帯合計 | |
| 加給年金(約39万円)支給される期間 | 227 |
| 妻65歳~(振替加算が約1.5万円) | 227 |
離婚する(26年分、分割した場合)
| 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 合計 | |
| 夫 | 78 | 70 | 148 |
| 妻 | 78 | 50 | 128 |
| 2人の合計 | 276 | ||
離婚する(12.5年間、3号分割のみの場合)
| 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 合計 | |
| 夫 | 78 | 92 | 170 |
| 妻 | 78 | 28 | 106 |
| 2人の合計 | 276 | ||
上の図表は高井さんの年金額について試算したものです。基本の年金額は夫が188万円、妻が88万円となります。妻は夫より2歳年下のため、夫が65歳で受給を開始してから2年間は夫に加給年金が約39万円、それ以降は妻に振替加算が約1.5万円加算されます。夫婦の合計は当初2年間は夫のみで227万円、3年以降は277万円となります。
離婚した場合、婚姻期間である26年分の報酬比例分(平均年収570万円とする)をすべて分割した場合、夫は148万円、妻は128万円となります。
離婚すれば加給年金などが支給されないため、夫婦の合計は276万円に減ります。3号分割のみなら、夫が170万円で妻が106万円になります。
高井さんの年金額は多くても128万円で、本人の金融資産がないと、生活が難しいと考えられます。また、夫から分割された年金を受け取れるのは、自身の年金受け取りを開始してから、という点にも注意しておく必要があります。
さらに、実家で母親と同居するなら、母親の介護を担うことになるのが現実的であり、母親の他界後も実家に居住する場合は、兄弟姉妹の合意も必要となってきます。実家以外に相続財産がなければ、実家を相続するために代償分割を求められることも考えられます。
今後の生活と老後、相続。この3つのステージについて慎重に確認していくことが重要になってきます。
親子といっても、仲良く暮らせるとは限らないので、まずは3か月程度、同居を試してみるのもいいかもしれません。そこで、仕事があるか、近所となじめるか、生活費がどれくらいかかるかなどを知ることもできます。
答えを急がず、慎重に考えていくことが大事になります。

まとめ
年金分割については、{基礎年金部分も分割できる、婚姻期間はすべて合意なしで分割できる、夫が支給開始になるのと同時に受け取ることができる}など、誤解が多いものです。
主婦の場合、離婚時にある程度の金融資産がないと生活に困窮する可能性が高いので、生活費や年金について具体的に試算していくことが重要になってきます。熟年層や妻が主婦の家庭では特に、離婚は経済的にダメージが生じやすいので、時間をかけての準備や婚姻継続の選択肢も残し、冷静な検討をしてみてはいかがでしょうか。











